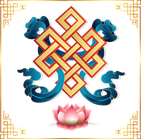悟りとは何か
ある雨の日、遠くの山を見ていた。
確かに、雨にけむる緑の山が見えている。雨音も、確かに聞こえている。
でも、見ているのが私であると、聞いているのが私であると、どうしていえるのだろうか?
古代ギリシャのソクラテスは「汝自身を知れ」と言った。これに対し、古代インドのウパニシャッド哲学者ヤージュニャヴァルキヤは「私とは認識できないものである」と説いた。中世フランスのデカルトは「我思う、ゆえに我あり」と言った。しかし、思っているのは我であると勝手に措定しており、我ありという結論を先取りしているに過ぎない。思っているのが我であるとどうしていえるのか、思っているのが我であると思い込んでいるだけではないか、そこには「思い」しかないのではないか、という懐疑にさらされる。従い、後の西洋哲学者は、疑うことができないのは思い(意識現象)のみであるとした。それでも西洋には「主体が客体を認識している」という抜き難い主客分離の構図がある。これに対し、ゴータマ・ブッダは「無我」を説いた。主客未分の世界認識である。東洋哲学では、西洋哲学より1000年も前に「思いあるのみ、ゆえに我なし」という真実に到達していたのである。
私は認識する「主体」であって、決して認識対象とはならない。認識主体が認識できるものは「客体」であり、すなわち認識主体以外のものであり、認識主体がその主体自身を客体として認識することはできない。認識主体Aを客体として認識するためにはAとは別の認識主体Bを仮定せざるを得ず、その別の認識主体Bを客体として認識するためにはそのBとも別の認識主体Cを仮定せざるを得ないのであり、認識主体が無限に遡及して、永遠に定まらないからである。
従って、私が自分で私自身を認識することは決してできない。包丁がその包丁自身を切れないように、指がその指自体を指せないように、私自身は私の認識対象とはなり得ないのである。逆に言えば、認識できる(と思える)ような自分とは、せいぜいが一秒前の自分像、すなわち過去の記憶としての自分のイメージに過ぎない。しかも、自我意識が生み出した、他者としての私である。他者としての私とは、他者の目から見た自分という、空想の産物である。実際に私が他者の目から自分を見ることはできないのであるから、架空であることは明らかである。そのような錯覚に過ぎない自分に執着することで、自ら悩み苦しみを生み出す愚かさを釈尊は戒めている。そこが仏教の要諦である。
しかるに、我々は皮膚の内側が自分であると勘違いし、その皮膚の外側は環境であって私ではないと決めつけ、勝手に自分と環境の間に境界線を引いている。この「私が外界を認識している」という主客二元の誤った世界観の中で、私が他者を認識するように、他者としての自分を私であるかのように錯覚しているに過ぎないのである。そこに登場する世界の中の私は、それを認識している主体としての私の正体ではない。
もともと人間の内側と外側に区別などない。空気・水・栄養を摂取し排出ている人体は開放系のシステムであり、人体と世界は連続し、その間には何の境界もないのである。すべては環境であるともいえるし、すべては自分であるともいえる。これを「自他一如」という。一如である以上は自も他もないのだ。ゆえに無我と同義である。無我とは我が全く無いという意味ではなく、我と我以外との間に境界が無い、限界が無いという意味である。無とは「無限」のことなのである。これを真宗では阿弥陀という。
もっとも、自分の意識の外には一歩も出ることができず、他人の意識の中に入ることもできず、自分の視点からしか世界を見ることできない(天上天下唯我独尊)。だが、世界が他でもない自分の意識の上にありありとした質感(クオリア)を伴って眼前している事実もまた疑いようがない。私自身は何の属性も帯びていないが(本来無一物)、山が見え、雨音が聞こえ、花が香り、果実を味わい、陽ざしの温もりを感じる、豊かな意識現象に満ち溢れていること自体は紛れもない真実である(無一物中無尽蔵)。
では、私は一体どこにいて、一体どこからこの世界を見ているのか?
もちろん私の頭(脳)の中からではない。脳の中に私の視点を置けば、その脳自体はどこにあるのかという問題が生じ、上記と同じ無限遡及に陥るからである。
この世界を映画に例えれば、自分とは「私の一生」という題名の映画を観ている観客である。ところが、そのスクリーンの中の架空の私に感情移入するあまり、自分自身が「私の一生」を演じているものと勘違いして、私の正体が単なる観客に過ぎないことに気付かないでいるのである。
私とは何か。それは認識できないものである。
認識できないものは対象化できないので、言葉で言い表せるわけもない。私たちは普通、五感で認識できるものを「有る」と呼んでいる。私自身は決して認識できない以上、「私は無い」というほかない。私とは何ものでもないもの(無)、というしかないのである。
坐禅は、認識できるような私は錯覚であり、私と私以外との間には境界はないのであって、もともと無我(=無限)であったことを悟るための修行である。坐禅の究極目的はただこの一点に絞られる。
坐禅により、主客二元の対立構図を生み出す思考(分析や識別)を止め、自我意識のフィルターを解体すれば、そこには意識現象のみの世界が広がる。主もなく客もなく、山を見ればそこには山しかなく、雨音を聞けばそこには雨音しかない。禅の覚者は、山を見れば自分が山となり、花を見れば自分が花になる、という(無我)。また、見える山は自分であり、見える花は自分であるといっても同じことである(唯我)。
金子みすゞは「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」と詠ったが、禅では「見えるけれどもないんだよ、見えていることしかないんだよ」となろう。
一般に我々は、モノがあるからモノが見えている、と信じて疑わないが、真実の因果は逆で、モノが見えているからモノがあると「推測」しているに過ぎない。我々は主観である五感の知覚を通してしか世界を把握することはできず、世界に直接触れることはできない。どうがんばってもモノ自体には到達できないのである。すると実在とは、モノがあることではなく、モノが見えていることである、というほかない。確実にあるのは見えていること自体だけであり、見られている客体としてのモノがあること、見ている主体としての自分がいること、そして自分がモノを見るという行為をしていること、これら3つはすべて「推測」に過ぎないのである。
冒頭の絵は音速を測定した物理学者マッハが描いた「マッハの自画像」と呼ばれるものである。自画像といえばゴッホの自画像のように鏡に映るような自分の姿を描くのが普通であるが、マッハはそれは自分ではなく、視野に表れたものが自分であるというのである。つまり、自分とは意識現象そのものであり、目に映るもの、五感に感じるものすべてが自分であることになる。そうすると、自分とは主でも客でもなく、自分には内も外もなく、自分と自分以外との間に境界はないことになろう。世界と私が一つになる。すべてが私である(唯我)とも、すべてが世界である(無我)ともいえるゆえんである。
数百年前に、道元禅師も同じ真実に到達している。
いわく、
仏道を習うというは、自己を習うなり
自己を習うというは、自己を忘るるなり
自己を忘るるというは、万法に証せらるるなり
万法に証せらるるというは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり
ここでいう「自己」とは認識主体としての私であり、「他己」とは認識対象(客体)としての私という意味である。言葉の上では区別できるが、認識主体としての私は決して認識対象とはならず、従って認識対象としての私とは単なる思い込みに過ぎないのであるから、そもそも主もなく客もない、主客未分であることに気付きなさいと言っているのである。
道元禅師の言葉を現代語訳すれば、
仏道修行は自己の正体を明らかにすることであり(己事究明)
それは自分が認識対象とならないということであり
それは自分と自分以外(環境)との間に境界がないということであり
それは認識主体としての自分と認識対象としての自分との分別を失わせることである
となろう。
古い経典にも、苦しみの基盤は「自分」という家であり、その作り手を見破れば垂木は折れ棟木は崩れて二度と苦しみは生まれない、という教えがある(ダンマパダ153-154)。道元禅師と同じことを違う言葉で表現していることは明らかである。
そもそも「主観」とは客観視点(無視点、超越的視点、神の視点ともいう)によって位置付けられた概念である。世界は「主客二元」ではなく「主客一元」「主客未分」であり、すべては客であるともいえるし、すべては主であるともいえる。すべてが客ならば主はないし、すべてが主ならば主は無意味となる。すなわち、「自己」も「他己」も同時に悟りによって解体されるべき架空の自分であり、そうして解体された後に残るものが私の正体である、というのである。
さきほどの「私の一生」という題名の映画に例えると、スクリーンの中の自分が「他己」、スクリーン自体が「自己」、観客が「私の正体」という関係になる。もちろん、その観客は客席にいるわけではなく、本当はどこにいて、どこから映画を観ているのか、知る由もない。映画が終わる前に、すなわち生きているうちに感情移入をやめ、人生が単なる映画に過ぎないことに気付き、どんなにスクリーンの中の自分が不幸であろうと、本当の自分とは無関係であることを悟るのが坐禅である。道元禅師のいう「身心脱落」とはそのことである。
(まとめ)
悟りとは、以下の真実を体得することである。
1 自分自身を認識することはできない(自分は認識対象にならない)
2 認識(意識現象)それ自体しか存在しない(認識主体としての自分もいない)
3 もともと自分と自分以外(世界)の間に境界はない(無限)